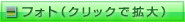◉震災発レポート
市民が記録した避難生活の日常
そこにある市内の情景、距離感、色彩
芦屋市・芦屋市立美術博物館 ◉ 2010年1月17日
カメラ・アイ 阪神・淡路大震災「市内の情景」記録写真展
text by kin
2011.1 up
美術博物館は遠かった…。
これまでも芦屋には何度か訪れたことがあったが、あまり街中を歩いたことはなかった。JR芦屋駅南口に降り立ち、初めてとなる芦屋市立美術博物館を目指す。しかし事前に調べたバス時刻表も、そのバス停の場所や経路が全然わからない。仕方がないので、ともかく美術館のある海の方向を目指して歩くことにした。かなり歩いて不安になりかけた頃、ようやく辿り着く。駅からけっこう離れた閑静な住宅地の一角に文教施設が集まっており、その木々の茂る図書館や谷崎潤一郎記念館と並んで美術博物館があった。
控えめな入口をくぐり建物内に入ると、まず最初に吹き抜けの大きなホールがあった。その壁一面にたくさんの写真が展示してある光景が目に飛び込んでくる。それを前にしたホールでは、ちょうど「震災語り部による『語り継ぎたい記憶』座談会」が始まるところのようだった。会場に入り2階テラスに上がる。壁面の写真を眺めつつも、耳は1階の吹き抜けから響く座談会の内容に傾けてみた。
そこにある市内の情景。構図、距離感、色彩
壁一面の写真は、芦屋市民から募集した「わたしと震災」という記録写真の数々である。当初はなかなか写真も集まっていなかったとの報道もあったが、結果的には500枚ほどもの数が集まっていた。私もこれに興味を覚え、今回訪れてみようと思ったのだ。この市民の写真を眺めていて気が付いたのは、倒壊家屋の写真が多いことと、人物を撮った写真があまりないことだった。
例えばこれが長田区の写真の場合では、広域にわたる全焼地区がいくつもあったため、焼け残った商店街アーケードやガレキの更地という写真の構図がとても多かった。また中央区であればビルの倒壊やオフィス街の被害といった記録が目立ったように思う。それに対してこの阪神地域の写真は、住家屋の全半壊の様子がとても目立った。これはもともとの街の特徴の違い、そして被災の特徴の違いが結果として現れているのだろう。
ここにあるのは、人や街の営みの記録ではなく被災の記録である。だが自分に置き換えた場合、自らの家や街が崩壊した姿を写真に撮れるだろうか。どの写真もが淡々と対象と距離を置き、客観として街を眺めているようでもあった。そのまるで見守るようなその距離感には、思わず感嘆を覚えた。
倒壊したガレキの色というのは茶や灰色といったモノトーンが主体であり、カラー写真であるにも関わらず被災倒壊写真にはあまり色彩感を感じない。しかし被災写真をこれだけ集めてみて見ると、そこに空の青さだけに色がついていることに気がつく。このような集積して展示することで、初めて気がつくこともあるのだ。
震災語り部座談会、被災した当事者から
100名ほどの聴衆が集まったホール会場では、震災時に芦屋にゆかりのあった人たちによる座談会が始まった。まず初めに阪神・淡路大震災と先日発生したばかりのハイチ地震の犠牲者に黙祷を捧げる。芦屋在住のハイチ育ちの芸術家であるヒューズ・ロジャー・マシュー氏も会場を訪れ、支援を呼びかけていた。パネリストには大学教授や前芦屋市助役のほか、芦屋で被災した映画監督の大森一樹氏がいた。現在も同市在住で大阪芸大教授も務める。そこで印象的だった同氏の発言要旨から抜粋してみたい。
自分はPTSDではないと思っていたが、ここにあるような被災写真を見ていると、涙が出てきてしまう。もしかしたらこれもPTSDの一つなのかもしれない。
昨晩やっていたドラマ(フジテレビ系・阪神・淡路大震災から15年『神戸新聞の7日間〜命と向き合った被災記者たちの闘い〜』1月16日21時放送)を見たが、関西弁とかいろいろ気になった点はあったがそれは置いておいたとしても、あれは「東京」で作ったドラマだ。こういうのは被災した当事者がつくるべきものだと思った。他人が客観的に作るものとは違うものだ。
最近、黒澤明の『七人の侍』について想うこと。あれは最後に武士が去り農民が残る話だ。震災を経た時に、はじめてあの農民の気持ちがわかった。震災で言えば、支援が去り住民が残った。これからは手を借りず、住民が生きていかなければならないだろう。
市民が記録した避難生活の日常
2階の展示室には、さらにいろいろな作品が展示されていた。最初にあったのが、芦屋市広報課による定点観測写真だった。行政が震災の記録として撮影を続けているのは、珍しいのではないだろうか。市内の33ヶ所を記録しているという。プロカメラマンのように全く同じ位置と画角と構図という精密さまでがあるわけでもなく、"ほぼ"同じ場所という程度のアバウトさであったのは市職員が撮っている愛嬌か。
そしてとりわけ驚いた写真が「芦屋市民による芦屋の記録」だった。これは座談会にパネラーとして参加していた高嶋敏展氏が始めたもので、被災した市民自身が撮影した震災の写真である。1995年3月、当時避難生活を送っていた被災者に使い切りカメラ100台を配った。そして集まった写真の中から50点を選び、全国を巡回して写真展を開催したのだという。
これと同様の企画としては、女優の黒田福美氏と水中写真家の中村征夫氏による長田区でのプロジェクトがあったが、あれは1995年11月だった。被災者自身の目線という意味では共にとても興味深いものだったが、こちらは震災から間もない3月のことだ。11月は仮設や更地といった復興過程の写真が多かったのに比べ、3月はまだ避難生活の真っただ中である。ここには絶対にマスメディアでは撮れないような、"避難生活の日常"が記録されていた。
共通するのはとにかくフレーム中の笑顔の表情である。笑顔は、倒れた家の前で、避難所で、自衛隊風呂の入口で、ボランティアの受付でと、至る所にあった。避難所となっていた学校は、避難民で一杯だった。そのため卒業式も体育館が使えず、テントの中で行った。卒業式の中で、同級生や家族の遺影写真と共に笑顔で収まっている写真もあった。そこには様々な感情が読みることができる。そこで見せた一瞬の笑顔は、遺影の中人に対しての卒業報告だろうか。
避難所の中でも子どもたちは遊ぶ。何でも遊び道具にしてしまう。非日常も彼らにとっては日常なのだ。仮設店舗の前や、避難所でみんな一緒に食事を準備している最中に撮った記念写真。そして倒壊した自宅や道路に走っていた亀裂…。
そこにあったのは、緊張の避難生活の中での弛緩の瞬間か、一時の安らぎか。被写体には、写真に撮られる緊張はあっても、心を閉ざしての身構えや硬直さはなかった。そこに映っていたのは、日常生活の記念写真と全く同様の遊びであったり照れであろう。まさに警戒心という壁のない、被災者"同志"に通じる"震災ユートピア"の中での優しさに包まれた家族写真のようなものだった。
生々しい美しさ
第二部のコレクション展「震災と美術」のほうには、堀尾貞治氏のパステル画「震災風景」シリーズが展示されていた。とにかく街の中に出て、時の使命感に背中を押されるように描写し続けた……そんなようなエネルギーを感じられる作品群だった。実に87点の内53枚もの作品が1995年3月からの4ヶ月のものである。そこには作者の言葉が添付されていた。
客観的に絵を見ていると、震災の風景の特徴と言うか、わかりやすいのは水平と垂直が壊れて×印、つまり、斜めの位置にものが存在している。これが基本形で、その次にあられもない物質のめげ具合が生々しい美しさを表しているのである。
それぞれの慰霊の姿
帰りは芦屋川沿いに出て、芦屋公園の松並木の中を歩いて行った。その公園の中ほどに、市が主催する慰霊の場「1.17芦屋市祈りと誓い」のテントが設営されていた。中心には巨大な石の組み合わさった句碑のモニュメントが鎮座している。時刻は遅めの午後に入っていた。すでに参列する人影もまばらになっている。一人、記帳と献花を済ませた。
会場を去ろうとしたとき、道路際に何台かのワゴン車が止まり、中から何組かの家族が降りてくるのが見えた。少し離れた所に住んでいるのだろう。わざわざ車に乗ってまでこの芦屋の慰霊会場に足を運び、追悼の祈りを捧げていた。それぞれの場でのそれぞれの慰霊の姿。被災地・芦屋を実感した一瞬だった。
[了]
淡交社
#文中に登場する名称・データ等は、初出当時の情況に基づいています。
◉データ
震災から15年
第1部 カメラ・アイ 阪神・淡路大震災「市内の情景」記録写真展
第2部 コレクション展3 震災と美術
開催日:2010年1月5日〜2月21日
場所:芦屋市立美術博物館(兵庫県芦屋市伊勢町)
展示構成
1. 市民の方々から募集した「わたしと震災」記録写真
2. 芦屋市広報課がとらえた「市内の情景」
3. ボランティアグループ「とまと」による伝えたい記憶
4. 美術博物館学芸員による市内の文化財・歴史資料調査写真
5. 日本赤十字社による災害支援活動の記録, ほか
震災語り部による「語り継ぎたい記憶」座談会
パネリスト:大森一樹(大阪芸術大教授)、中野正勝(前芦屋市助役)、
廣瀬忠子(芦屋市婦人会長)、高嶋敏展(写真家/元芦屋市ボランティア
委員会写真記録部長)、明尾圭造(芦屋市立美術博物館学芸課長)
コーディネーター:角野幸博(関西学院大学教授)
- 芦屋市立美術博物館
- [2010/01/05]色あせぬ被災者の記録 芦屋で市民撮影の写真展(神戸新聞)